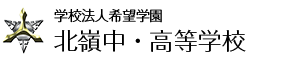北嶺で学んだ先輩達はまさにグローバルな活躍をしています。 それを知ってもらい、後輩達にも将来、世界中で活躍してもらいたいと思います。
北嶺25期生の齊藤明良と申します。
2017年に国際医療福祉大学(IUHW)医学部医学科に入学しました。
2022年に米国ペンシルベニア州にある、ピッツバーグ大学医学部(UPMC)とピッツバーグの市中病院Excela Health Westmoreland Hospital(EHWH)にて卒前臨床実習を行い、2023年にIUHWを卒業しました。現在(2023年9月時点)、IUHW成田病院にて初期研修医として勤務しています。
まず、私の出身大学について説明させてください。
IUHW医学科は2017年に新設され、1学年140人、そのうち20人をアジア各国(ベトナム、ミャンマー、モンゴル、カンボジア、インドネシアなど)の留学生が占めています。また、医学の授業は一通り英語で行われます。そんな変わった大学に1期生として入学しました。
入学後、留学生と一緒に寮生活をしながら、勉強に励みました。
中高6年間を北海道の山の中で過ごしてきたのに、急になんだかグローバルな環境にきてしまったなぁ、と考える大学生活。多様な価値観に揉まれているうちに、海外で医師として働きたい、と考えるようになり、米国医師免許を取得するための準備に取り掛かりました。

カンボジア留学生の同級生とアンコールワットにて
米国医師免許試験については、普段から医学英語に慣れていたこともあり言語の違いに苦しめられる場面は少なかったと感じています。しかし、卒業後の研修やキャリアについての最近の情報が不足していました。そこで、北嶺の谷地田校長先生、郷頭教頭先生からご紹介いただき、15期生松井甫雄先輩に連絡をし、米国医師免許試験(USMLE)の勉強法やアメリカの研修システムについて教えていただきました。そのおかげで、米国医師免許の1段階目を突破。夢へ大きく前進しました。
その後、6年生の夏、UPMC麻酔科とEHWH心臓外科にて海外実習を行いました。実習中は研修医、教授と、目の前の患者さんについてディスカッションをする機会もあり、医学的根拠に基づいた自分の考えを発信することができました。救急救命の筆記・実技試験に合格することもでき、それまで学んできたことが現地でも通用する、と実感することができました。米国の医療システムや研修トレーニングについても学び、将来的に日本だけでなく米国式のトレーニングも受けたいと考えるようになりました。

ピッツバーグ大学のメイン校舎 cathedral of learning
私は脳神経外科を志しています。
外国医学部出身者が米国で脳神経外科として働く、というのは非常に競争率が高いため困難といわれています。将来どうなるかは、まだわかりませんが、どこかで北嶺の皆さんに出会えることを楽しみにしています。

現在の勤務先IUHW成田病院にて

初夏のカロリンスカ大学病院
2003年に北海道大学医学部を卒業して、研修医期間を経て外科医として北海道内の病院で働き始めました。その後、大学院に入学し基礎研究で博士号を取得して、地域の拠点病院にて一般外科として働いてきました。3年前より北海道大学の消化器外科IIにて助教の職を得る機会があり、肝胆膵外科医として働いております。
高校生の頃に北嶺の海外修学旅行でバンクーバーへ行った経験から、その後も漠然と海外で生活するチャンスがあれば挑戦してみたい気持ちがありました。そんな中、日本の医師免許のみで臨床医療ができる数少ない国の北欧で働くことができました。2017年4月より1年半の間、スウェーデンのカロリンスカ大学病院の膵臓外科で臨床医として現在働いております。
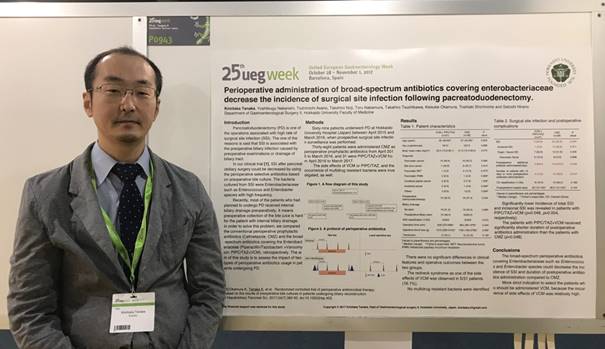
バルセロナでの学会発表
日本人には、スウェーデンを含めた北欧の国々についてあまりなじみがないと思いますが、カロリンスカ研究所はノーベル賞の授賞式でも有名な大学です。日本から研究者も数多く来ております。また、スウェーデンは多くの移民を受け入れて経済を発展させている国でもあるので、今いる職場でも出身地が様々な国の医師で構成されています。また、気候も北海道と非常に似ており、スウェーデン人の人柄もなんとなく日本人に似ているところもあります。
日本の医療は確かに素晴らしいものが多く、特に外科手術の技術に関しては世界からも注目されております。日本の多くの外科医は海外で働く意義はないと考えているのも事実です。しかし、欧米にも非常に高い技術を持つ医師や、日本にはない考えを持つ組織に出会える事は、海外で働くことの醍醐味ではないかと思います。日本で培ってきた経験と海外での新しい価値観が合わさることは、新しい考えが生み出される素地になります。こういった小さな変革の積み重ねが今の素晴らしい日本を作ってきたのも事実です。

手術室での若手外科医への指導風景
これからの日本は急激な労働人口の変化からどんな仕事を選んでも国際化が必要になる場面があると思われます。私もいち臨床医として数年前まで北海道で働いていたのですが、ちょっとした運命から今の立場で働いています。今の北嶺における教育方針は、私が在籍していたときよりもグローバルな視点に立ったカリキュラムが構成されております。いま北嶺で学ぶ、またはこれから学ぶ皆さんには、チャレンジをする高い志と選択する勇気を持っていれば、世界で活躍する道が開かれていくと思います。近い将来皆さんと北嶺ファミリーとしてお会いできることを楽しみにしています。
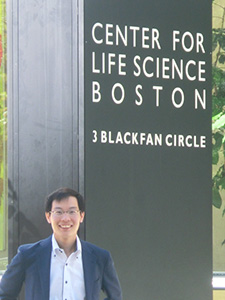
職場の前で
私は2006年に大学を卒業し、研修医を経て、2008年に北海道大学大学院医学研究科内科学講座 免疫・代謝内科学分野に入局しました。数年間の病院勤務を経て大学院を修了し、2015年からハーバード大学医学大学院 ベスイスラエルディーコネスメディカルセンターで研究させていただいています。私は膠原病という病気を専門にしています。膠原病は、自分自身の体の構成成分と反応してしまうリンパ球や抗体などが認められる自己免疫疾患で、皮膚、関節、血管、筋肉など全身の臓器に障害をきたす原因不明の病気です。
医学は日々進歩していますが、未だ病態が不明な病気や適切な治療がみつかっていない病気がたくさんあります。臨床医として働くこともとてもやりがいがあり、天職のように思っておりますが、現在の医学では如何ともしがたい場合が多々あることを感じ、早期診断や治療に結びつく研究もしたいと思うようになりました。また留学することで、医師として、研究者として、人としてまだまだ未熟な自分を鍛え、より人の役に立つことがしたいと思い留学を決意しました。
私が留学している研究室は6期生の吉田修也さんも留学中です。同じ医局の先輩でもあるのですが、これまで一度も一緒にお仕事をさせていただいたことはありませんでした。奇しくも私は留学先で、吉田さんと同じプロジェクトの研究をさせていただけることになりました。まさか吉田さんとボストンで一緒のプロジェクトをさせていただけるとは考えてもいませんでした。
北嶺では同期は当然のこと、先輩、後輩ともいい関係を築くことができると思います。卒業後に様々な分野で活躍している姿をみて、いつも刺激をもらっています。また職場で一緒になることもよくあり、とても心強いです。北嶺で過ごすことができるみんなとの時間を大切にして、ぜひ楽しく充実した6年間を過ごしてください。また実際に決めることはなかなか難しいと思いますが、早い時期に自分の一生を捧げられることはなにか考えてみるといいかもしれません。最後になりましたが、いつも我が子のように熱い気持ちで接してくださった先生方に心より感謝いたします。

コスタリカのテレビ番組で日本の文化を紹介する山口さん
これまでスペイン、ベネズエラ、コスタリカで8年間働いてきた中で、どの国でもよく聞かれる質問がいくつかあります。「日本と中国の違いは何ですか?」誰でもわかるように見えますが、地球の裏側にある中南米には日本人があまりいないので、意外とわからない人が多いのです。中には、日本人はまだサムライ、ゲイシャだと本気で思っている人もいます。でも無理もない話で、日本でも、ブラジルとメキシコの違いを言える人は少ないでしょう。地域や国が違えば文化も違い、考え方も全然違います。わかっているつもりでも、実際に行ってみると思っていた以上に違うものです。隣の中国や韓国のことさえ、私たちはテレビを通してしか知らないことが多いですね。
もう一つ質問。「日本人の宗教は何ですか?」これもよく外国人によく聞かれますが、未だに私はこれに答えられません。仏教なのか神道なのか、でも実はどちらの宗教もよくわからない。外国人から日本のことを聞かれると、自分が日本のことにあまりにも無知だったことに気づかされます。「日本人が時間に厳しいのはなぜ?」「日本人は高齢者を敬うって本当?」「日本人は電車に乗るときなぜ走るの?」これらの質問に皆さんはどれだけ答えられますか。
日本の外に出ると、外国のことだけでなく、日本そのものについても学ぶ機会があります。その中で、日本人的な考え方や生き方が「唯一」のものではないことに気が付き、色々な生き方の中から自分に合ったものを選ぶための選択肢が増えます。まずは外に出てみませんか。違う言語、違う考え方、違う生き方を見るのはおもしろいものです。

オーストラリアでの勤務がすでに7年になる坂井さん
大学卒業後、世界で働く舞台を求めて、総合商社に入社し、現在オーストラリアのブリスベンという都市に駐在し、製鉄原料の石炭(原料炭)資源の投資ビジネスに携わっています。帰国子女ではない自分が、日々、オフィスで一緒に働く現地採用の同僚社員、資源メジャーのパートナーと英語で議論するという姿は高校時代には想像もしていませんでした。
振り返って考えてみると、世界の舞台で働きたいという希望を持ったのは、北嶺での英語授業が一つのきっかけだったと思います。
通常の座学の読み・書きの授業だけではなく、ネイティブの先生による会話中心の授業、カナダ・アメリカでの2週間の語学研修と、受験のための英語だけではなく、世界を垣間見れる体験をさせてもらいました。グローバルな世界で政府も企業も競争することが求められている中、受験のためだけではなく、将来を見据えて真摯に指導して下さった北嶺の先生方にはとても感謝しています。

中国・青島の製紙会社で商談を行う吉田さん(右から2番目)
北嶺の国際色豊かな授業や教育方針が私の人生に大きく影響しています。まるで世界各国を飛び周った様な感覚にしてくれるダイナミックな地理の授業やネイティブの先生による英語の授業。「コスモポリタンになれ」と生物の先生がおっしゃっていた事を今でもよく覚えています。
また、北嶺の一大イベント修学旅行で異文化に直に触れた事は非常に刺激的でした。たった2週間ですが、帰国後に「海外を舞台に仕事がしたい、海外に住みたい。」漠然とそう思う様になりました。その思いは大学でも変わらず、総合商社で働く事を選びました。
現在、私はチップ・パルプ部に所属し、パルプの輸出と三国間ビジネスを担当しています。輸出は日本のパルプを中国とマレーシアへ販売、三国間はインドネシアのパルプをインドネシア国内、マレーシア、タイ、フィリピン、ベトナムに販売しています。販売顧客が全て海外である為、月の半分以上は海外で過ごしています。言語・文化・ビジネス習慣が違う客先にパルプを販売する事は、決して簡単ではありませんが、やりがいがあり、充実しています。
最後に、北嶺ファミリーは皆非常に仲が良く、今でも同級生と食事をしたり、学年を超えて集まりフットサルしたりする事もあります。仕事のきっかけや友人に至るまで北嶺で得た貴重な財産に感謝しています。

丸紅で吉田さん(左端)と同じ部署で働いている15期の土井川さん(東大卒)(右端) ※100km駅伝に参加した時の写真

有川さんとエジプトの三井物産現地エージェントの方
私が北嶺で学んだことは、自分が個性的に生きることの大切さ、そして個性的な人から学ぶことの大切さです。
我々の代である10期生には今思い返しても本当にいろいろな同級生がいました。そして皆がその個性を自由に発揮していたと思います。そんな多様な同級生といろいろな場面で一緒に濃密な6年間を過ごす環境は素晴らしいものでした。北嶺での生活の中でいろいろな人に興味を持ち、自分も興味を持ってもらいたいという気持ちが強くなりました。加えて出来るだけ自分の知らない世界に飛び込んで、そこの住人と話す楽しさを学んだのも北嶺でした。
理系命だった私が学園祭でのストリートダンスをきっかけに、大学では生活の殆どをダンスの仲間たちと過ごすことになったのも北嶺でのそういった経験が背景にあると思っています。自分と異なる人たちと仲良くなりたい、仕事がしたいという思いを持って就職活動をした結果、総合商社と呼ばれる職種の会社に入社しました。入社してからは中東とアフリカ向けの農薬の輸出を担当して日本の農薬メーカーと現地の農家を訪問し、現在は会社の制度で、ブラジルで勤務しており、鉄道のビジネスを担当しています。
ブラジルは歴史的背景からインディオ、黒人、白人、アジア人(日系人が世界で一番多いのは日本から一番遠いブラジルです)が混在しており、世界の中でも特に多種多様な人が住んでいる国の一つです。自分が知らない分野で、自分が話したことの無い人たちと一緒に仕事が出来る総合商社という会社は、自分にとって非常に刺激が多くやりがいがある仕事です。
私見ですが、人間が最も成長するのは出来るだけ自分と違う人と会い、自分の考え方に出来るだけ大きな衝撃を受けた時だと思っています。その経験で考えが変わるのも良し、それでも自分の考えが正しいと思うのも良し、どちらにしろ自分自身を深くしてくれるのではないでしょうか。特に中高生時代のそういった経験はより一層自分を成長させてくれると思うので、北嶺時代はいろいろな事・人に興味を持って飛び込んでみたらどうかなと思います。

ブラジルのストリートダンスの仲間と有川さん

アブダビ郊外の砂漠にて
中東の産油国であるアラブ首長国連邦(UAE)の首都アブダビに駐在し、石油開発技術者としてアブダビ沖洋上における石油掘削作業に従事しています。UAEはサウジアラビアに次ぐ2番目に大きな日本の原油輸入先であり、多くのタンカーが日々日本へ向けて出港していきます。夏は気温が50度にもなる灼熱の地であり、札幌とは環境が180度全く異なりますが、日々充実した社会人生活を送っています。石油の乏しい日本では石油開発と言ってもあまりピンとこないかもしれませんが、世界的には主要産業としてグローバルな業界であり、私が現地で勤務している会社には約40国籍もの人種も宗教も異なる人達が働いており、まさに人種のるつぼの環境下で仕事を行っています。
UAEはイスラム教が国是であり、毎年イスラム暦の9月のラマダンと呼ばれる1ヶ月間は、イスラム教徒の義務の1つである断食として、日中は飲食を絶つ事が求められ、私達のような非イスラム教徒も公共の場所での飲食は慎まなければなりません。朝から晩まで水さえ飲めない環境に慣れるまで、最初は本当に大変でした。
このような異国の地において、文化も生い立ちも異なる多種多様な人達との共通言語は英語になります。しかしながら、英語が母国語でない人達は皆、私も含めて決して流暢な英語を話すわけではありません。文法やスペルが間違っていようが全く気にせず、自分の主張を正々堂々と一生懸命に述べる多くの外国人に囲まれながら感じるのは、決して正確な英語を話す必要などなく、むしろ筋と情が通っていればお互いに理解し合え、皆が納得するのです。すなわち、話す術云々よりも、話す内容、突き詰めていけばその人の誠実さそのものが問われているということでした。アラブ人はもともとベドウィンと呼ばれる砂漠の遊牧民で、見知らぬ相手を瞬時に見抜く能力に長けています。
北嶺ではこの話す術、すなわち勉強だけではなく、柔道やラグビー、海外研修といった多くの気づきを与えてくれる環境がたくさんありました。また、大学生、社会人時代を振り返ってみても、北嶺の友人ほど個性豊かな仲間達には未だ巡り合えていません笑。後輩の皆さんには、北嶺2000日を1日1日大切に過ごせば、何も心配することはないことをお伝えしたいです。

取引先の関係者と(右から3番目が本人)

Stanford大学病院正面玄関前

キャンパス内の広場にて
私は医学部卒業後、日本で初期研修医として2年間、循環器内科医として6年間勤務しました。循環器内科は心臓血管領域の循環器疾患を対象としますが、中でも私は狭心症や心筋梗塞といった冠動脈疾患の薬物治療、カテーテル診断・治療のトレーニングを重点的に行いました。現在の医療はこれまで先人たちが積み上げてきた経験と研究により得られた知見に基づいて行われております。したがって、医師は臨床経験を積むと同時に、常に勉強し、最適な診断・治療法に関しての技術・知識をアップデートしていく必要があります。私はこれまでの知見を利用するだけでなく、自らも今後の医療に役立つ知見を発信していきたいと考え、医師9年目より米国で心血管疾患のカテーテル診断・治療に関する臨床研究に従事しております。
北嶺は1学年120人程と比較的少人数であり、先生方からの密なフォローアップと各々に適した学びの機会を提供してくれる場所でした。札幌の山の上で北嶺ライフを送るファミリーとして一丸となり、勉学・ラグビー・柔道に男くさく励んだのは良い思い出です。今でも、日本や世界各地で様々な分野で高い嶺を目指す北嶺時代の友人からは良い刺激をもらっています。皆さんも北嶺ライフをどうか存分に満喫してください。そして、近い将来、皆様と北嶺ファミリーとしてお会いできることを楽しみにしています。
私はカンボジアで人材紹介会社を経営しております。創業から1年半の新しい会社ですが、社員数は日本人・中国人・カンボジア人合わせて合計30名おり、社員規模で言えばカンボジア国内で最大の人材紹介会社となっております。大手商社様などを含む計180社が取引先です。
カンボジアの一般的なイメージである地雷・内戦・貧困というものとは、かけ離れている生活が首都プノンペンには起きています。2013年経済成長率7.3%。急成長するASEANマーケットの中でも、最も早い経済成長を遂げている国です。カンボジアの平均年齢は23歳。日本の平均年齢44歳と比べると21歳も若い世代で構成されていると言えます。また、日系企業の例では、東南アジア最大のイオンモールが2014年7月にオープンしたばかりです。意外かもしれませんが、既にモール内にはWATAMI、銀だこ、吉野家などの有名日系企業が入っています。


今さんの誕生日祝いをしてくれている社員の方達と
目指すなら高い嶺。人口1500万人の小国ですが、その分「カンボジアNo.1の人材企業」の地位を取れると考えています。当然、アウェーの地でビジネスを作るわけですから、うまくいかないことや大変なことも多々あります。そんな中、「努力する」ことができるのは、中高時代に「努力した」経験があるからだと感じています。
北嶺は努力する場をたくさん提供してもらえる学校です。授業以外の講習や添削、全校登山、学校祭、ラグビーや柔道。こんなに幅広いフィールドを与えてもらえる学校は他にはありません。
また私は6年間青雲寮に入っていたので、日々の生活のすべてが貴重な経験となりました。ふと世の中を見渡すと、もしかするといまの日本には世界での高い嶺を本気で目指している人は多くないかもしれません。そんな世の中だからこそ、北嶺卒業生として世界をフィールドにさらなる高い嶺を目指していきたいと思います。

プノンペンにある今さんの会社の社員の方達と勢揃い

現地の事務次官の方と親交を深める美甘さん 「色々大変だけれど、明日は今日よりも楽しいって実感できる毎日さ。」私が駐在するアフリカ最大の国であるナイジェリア・ラゴス州で、タクシーの運転手さんから聞いた言葉です。直後に訪問した州の大臣にこの話をしたところ、「自分は様々な改革に取り組んでいて批判も多いが、少しでも役に立っているとわかりとてもうれしい」と目を赤くして喜んでいました。
私の仕事は、先の大臣のように国のため、国民のためを思って活動する開発途上国のリーダーたちをサポートすること、サポートするために日本政府の資金を活用して良いプロジェクトを形成し、それらをマネジメントすることです。20代で相手国の大臣や政府高官と話をすることは度胸がいりますし、また自身の専門分野外のことでもニーズがあれば同僚や専門家の力を借りつつ必死に勉強し、日本人代表として恥ずかしくない解決策を提案しなければいけません。めざす嶺が高すぎると思うこともありますが、つらいときは日本や世界各地で活躍する北嶺時代の友人たちの姿を胸に、負けるものかと、やりがいのある刺激的な日々を楽しく過ごしています。

私が北嶺で学んだことは、勉強面ももちろん大きいですが、精神面が一番大きいと思います。「石の上にも三年」と言いますが、とにかく我慢して物事に打ち込むことを私は北嶺を卒業した後も実践しています。
私は2006年3月に北嶺を卒業した後、大学へ進学して、交換留学生として中国・蘇州に2年間留学をしました。元々、学部生で2名しか選ばれない狭い枠でしたが、必死に勉強に打ち込んでその枠を勝ち取りました。
留学してからは、授業はもちろんですが、積極的に日中交流活動や中国人学生との交流を行い、請われて参加したスピーチコンテストでは蘇州地区第3位に入賞して、現地の大学からも日本の大学からもお褒めの言葉をいただきました。
帰国後は、かねてより勉強していた教育者への道を進んでいましたが、国際舞台での活躍という夢も捨てきれずにいました。そんな時に、目に入ったのが「日本語教師」という仕事でした。「教育者」「国際舞台」という二つの夢を叶えることができる理想の仕事でした。
そこで、わたしは学校教育の道はすっぱりと諦め、3年間一般企業のサラリーマンとなり、一生懸命に貯金しました。そのお金をすべて使い、日本語教師の資格を取得するため専門学校に通い、2016年4月より夢を叶え、「第2の故郷」中国・蘇州において日本語教師としてスタートを切りました。
3年間、夢のため我慢して頑張ることができたのは、やはり北嶺において鍛えられた精神力があったからだと確信しています。北嶺では「校技」として柔道・ラグビー、そして受験に勝ち抜くための先生方の厳しい授業を通して精神が鍛えられました。そして、私は親元を離れ青雲寮で生活していたので、人に負けない自立心は早くから身についていたと思っています。
夢を叶えたとはいえ、まだまだ私は未熟者であり勉強をしている段階です。もっと大きな存在になろうと日々努力を怠っていません。今、北嶺で勉強している後輩たちも我慢強く打ち込むことによって、未来を開いていってほしいと思います。
最後に私が大事にしている言葉を送ります。「夢は見るものではなく、自身で叶えるものである」。


私はまだ「世界で活躍」しているというほどの実績も経験もありませんが、 将来を担う北嶺生の力に少しでもなればと考え、恐縮ながら寄稿させて頂きます。
1、自己紹介
北嶺時代は6年間青雲寮で寮生活、部活は生徒会、ディベート部、柔道部に所属

タイ東北地区の営業所で従業員に28歳の誕生日を祝って頂きました。右から3番目が私です。
2、現在の仕事内容
タイにおける自社の販売組織の支援。味の素株式会社は世界130国以上の地域で商品を販売するなど事業をグローバルに展開しています。私の仕事はタイの販売組織の売上と利益が最大になるように考えること、加えて長期的にみて自社が従業員のかたやタイという国にどのように貢献出来るかを考えていくことです。支援といっても、オフィスの中でパソコンとにらめっこをするわけでなく、自ら販売の現場に出てタイの従業員と一緒に解決策を模索していきます。気温が30度を超えるタイの現場を、タイ語を使って走り回ります。心と身体が熱くなる最高の仕事です。
3、中高校生の皆さんに伝えたいこと
「いま目の前にあることに全力で取り組む」
実は、私は高校時代には、将来、自分が海外で働くことを想像すら出来ませんでした。大学を卒業してから、毎日を一生懸命に働いた結果、会社から海外で働くチャンスを頂きました。 10年後の自分の姿を明確に思い描くのは非常に難しいと思います。社会に出る前の中高校生の皆さんにとっては、なお難しいと思います。ですから、まずは、目の前にあることに全力で取り組んでみてください。皆さんの場合は勉強や部活かと思います。将来の夢がしっかりと決まっていなくても構いません、むしろ決まっていないほうが普通です。毎日の努力が必ず皆さんの将来の可能性を広げます。いま全力で努力できれば、きっと夢に近づきます。 最後にこの場を借りて在校時代からお世話になった北嶺の先生方、青雲寮の寮監の先生方に改めて御礼申し上げます。
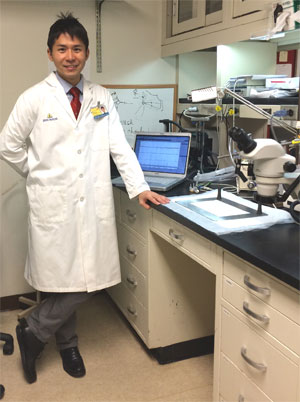
ジョンホプキンス大学の研究室の松井さん
北嶺中・高等学校(北嶺)を15期生として卒業いたしました松井甫雄と申します。2006年に東京大学(東大)教養学部理科三類に入学し、2008年に東大医学部医学科に進学しました。2011年にジョンズ・ホプキンス大学医学部(JHMI)で卒前臨床実習を行い、2012年に東大を卒業しました。
医学部卒業後は東京大学医学部附属病院(東大病院)で初期臨床研修を行い、研修医2年目には国立保健医療科学院へ派遣していただき、スイス・ジュネーブの世界保健機関(WHO)本部やフィリピン・マニラのWHO西太平洋事務局での研修の機会も得ました。初期研修修了後の2014年度からは東大病院を離れ、米国メリーランド州ボルチモアにあるJHMI泌尿器科でポスト・ドクトラル・フェローとして勤めております。
日本では余り知られていないかと思いますが、JHMIは全米医学部ランキングで毎年トップに選ばれているところです。JHMI附属の病院も全米のみならず、世界トップレベルの病院として有名です。
若干、カリキュラムは変わっているようですが、東大医学部では5年生の時に日本国外で臨床実習をすることができます。私のときはJHMIとミシガン大学と正式な交流協定があり、それ以外にもハーバード大学やペンシルベニア大学といった、他の米国医学部へも先方の選考に合格すれば、留学することができました。
JHMIに行けるのは毎年東大医学部から2人だけで、倍率の高い学内選考を通らなければいけません。また、JHMIのあるボルチモアは治安が極めて悪いところと聞いていたので、他の米国医学部に行こうと思っていたのですが、何だかJHMIへの派遣が決まってしまい、2011年に交換留学生としてJHMIに来ました。このときの体験談は東大医学部国際交流室のウェブサイトに掲載されていますので、参照ください。
この実習のときから、前立腺癌手術の術式を確立された、恐らく世界で一番有名な泌尿器科医であるパトリック・ウォルシュ先生との交流がはじまりました。2011年4月の日本泌尿器科学会総会でのウォルシュ先生の特別講演の予定があり、このスライドを日本語に訳すという仕事を賜りました。3月初めには全てが出来上がっておりましたが、3月11日の東日本大震災とその後の原発事故とで、ウォルシュ先生の来日も一旦白紙となりました。私は3月末まで米国で実習をしておりましたが、4月に帰国してからは日本国内の状況を毎日電子メールでウォルシュ先生に連絡し、名古屋は安全であることをお伝えしました。何とか総会当日に名古屋でお会いすることができ、私の作ったスライドも役に立つことができました。
この名古屋での再会の際に、「アメリカで泌尿器科の臨床研修を6年間やらないか?」とウォルシュ先生に尋ねられました。医学部在学中にアメリカの医師免許試験は既に合格していましたので、決して無理な話ではなく、ありがたいことであったのですが、「アメリカでの臨床研修を外国医学部出身者が行うというのは極めて競争が激しいもので、難しい気がします。」と答えました。「だったら、日本での研修が終わってから、ひとまず、1年か2年、アメリカで研究しないかね。」と言われ、とりあえず、お返事は臨床研修をしながら考えることに致しました。
卒後初期臨床研修をする中で、日本の医学・医療を世界に発信するためにも、良いか悪いかは別として、世界の標準であるアメリカの医学・医療を体験しなければいけないと考えるようになりました。2013年5月にウォルシュ先生に再度連絡し、2014年度からJHMIに戻ってくることになりました。

スイスのジュネーブにあるWHO本部で研修する松井さん
現在は前立腺癌や膀胱癌術後の合併症治療についての研究を行っております。分野としては癌研究や再生医療とも関わりのある内容ですので、JHMIの他の診療科と連携をしながら、学際的な研究をしております。研究を手伝いにくる学生の指導など、教育に関わる機会も得ています。研究の詳しい内容についてはJHMI泌尿器科のウェブサイトに寄稿していますので、ご参照ください。

松井さんが勤務するジョンズ・ホプキンス病院
JHMIが世界初というものは多く 、そもそも臨床研修(研修医が病院に住みつく様子から、居住という意味でレジデンシーと言います)はここからはじまり、手術で手袋をするという習慣もここで生まれ、最初の成功した心臓手術もここで行われました。ノーベル賞受賞者やラスカー賞受賞者も多数輩出しており、名実ともに世界のトップと言えます。ここで働くのは中々、大変なことも多く、辛いときもありますが、やりがいが十分にある経験が沢山できるところです。
是非、国際的に医師の仕事がしたいという方がいらっしゃれば、東大医学部のJHMIとの交換留学プログラムをご検討くだされば幸いです。東大以外にも、日本の医学部で同様プログラムを持っている所もあるようですので、ウェブサイトなどで確認してみてください。
若気の至りから、東大医学部を飛び出して、米国に来てしまい、この先どうなるかは私も分かりませんが、北嶺の皆さんにJHMIでお会いできれば嬉しいです。
2015年に京都大学大学院にて化学工学を修了したのち、サントリーにてアルコール製品の商品開発部署に在籍し、香味設計や生産設備設計を担当しておりました。基本的には国内業務に従事していましたが、国外の技術を活用するために必要に応じて海外の工場やメーカーともやり取りしていました。私は特に蒸溜技術を専門にしており、北南米や欧州の蒸溜所を訪問して酒造りに関する技術交流を行ったり、欧州の設備メーカーを訪ねて現地の技術者と議論しながら蒸溜器の設計を経験したりもしました。専門性が同じ人同士であっても国によってプロセスや習慣が異なることも多く、言語以外の面でも意思疎通がうまく取れないこともあり、大変苦労しながら仕事をしたことを覚えています。

2021年の夏からアメリカのコロンビアビジネススクールに留学しています。これまでの生産開発部門での知識や経験に加えて、会社をより多角的に見るための経営的な視点を養うとともに、海外拠点でも活躍していく上で海外のビジネスを学びたいという思いもあり、30歳を過ぎて2回目の大学院進学を決めました。

ビジネススクールではネイティブスピーカーに囲まれて授業を受け、ディスカッションやグループワークをこなす日々です。出身地も経歴も様々なクラスメートとともに過ごしていると自分の世界や視野が日々大きくなっていくことを痛切に感じます。自分が想像もできないような”常識外“の世界を知ると同時に、相対的に自分のアイデンティティを見つめなおす機会にもなります。コンテキストの高い日本を飛び出して、海外で切磋琢磨しないと絶対に経験できないことだと思います。
私自身、海外経験は多くありませんでした。北嶺の修学旅行が初めての海外経験で、それがきっかけで漠然と海外に対する憧れが湧いたように思います。おかげで大学院生の時にヨーロッパで数ヶ月インターンシップするチャンスがありましたが、あまり深く考えずに手を挙げて行くことができました。その後、社会人になっても英語の勉強を細々と続けていると海外出張や海外案件を任せてもらえるようになり、最終的には今に至ります。私は30歳を過ぎてから本格的に海外生活をスタートさせることとなり、もう少し早く海外に出たかったな、という思いはあります。一方でスキルや経験をある程度積んでから、語れるものや他人に負けないものを持って海外に出ることができました。自分のキャリアに後悔はないのですが、もっと若くから訳も分からず海外に出てみるという選択肢もあったかもしれません。私が在学していたころに比べ、北嶺にはより洗練され、内容も濃い海外プログラムがあるようですので、より明確な目標を描き、思い切りよく世界に羽ばたいてほしいと思います。
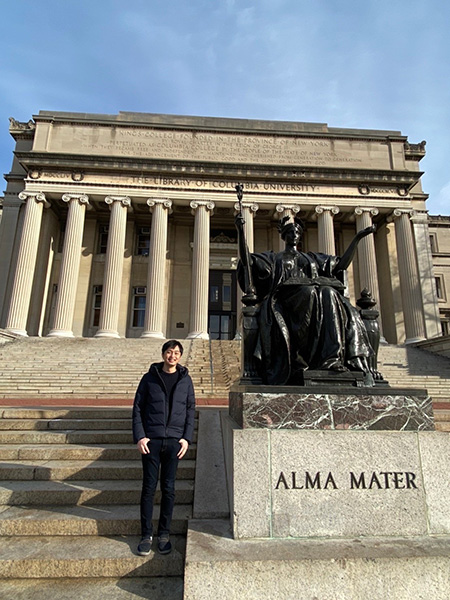
1. 「世界で活躍」すること
ウェズリアン大学は、米国 東海岸の名門小規模大学群リトルアイビーの一校です。大学では、世界中からのエリート達が集結しています。様々な環境で生まれ育った生徒が、様々な環境、階級出身のアメリカ人学生と共に、宗教、人種、文化を超え、『人と人』として学び合い、ふざけ合い、たまには喧嘩もしながら共同生活をしています。 私は社会科学部(College of Social Studies)に在籍しています。社会科学系と人文系の分野を幅広く履修した後、興味のある分野を中心に知識を強化するというプログラムです。私の場合は、制度経済学(Institutional Economics)という分野の研究・勉強をしています。 課外活動は、高校時代からの柔道を継続し、地元のクラブ等で指導・練習をしています。2年前に、大学紹介ブログ、「Japan At Wesleyan」も立ち上げ、同じ北嶺の卒業生の植村君が在籍するブラウン大学の「ブラウンの熊」というブログと、日本での留学関係ブログランキングの1位2位を毎週争っています。 そんな私の経験から思う事があります。それは、広い視野をもって、社会的なプレッシャーや一般常識にとらわれないことの重要性です。日本で価値があると思われているものが、外の世界ではなんでもないものだということはよくあります。海外や日本に関わらず周りに流されてはいけません。狭い視野では、その視野のなかでしか物事を考えらないため、周りの環境に対して盲目的になってしまいます。


2. 北嶺での経験
私は北嶺で、「自分で考える」能力の土台を築きました。悩みがあるときは、 親切な先生方が息子の事のように相談に乗ってくれました。自分が思い立ったこと、挑戦したいことは、学校の利害に関係なく全力でサポートしてもらい、成功した暁には自分のことのように喜んでくれました。そのような、「挑戦が許される環境」で、いろいろな事に何度も挑戦し、その度に成長することができました。私にとっての北嶺とは、自分で考える習慣と、それを実践できる自力を養った場所でした 。
日本では、「グローバル人材の育成」ということが騒がれ始めているようです。しかし、グローバル人材とは、英語が話せる人でも、海外で生活する人の事でもありません(英語が話せる事は当たり前のことです)。自分の出身環境に関わらず、いろいろな視点や考え方を理解し、それを統合実践できる能力をもった人材が世界で活躍できるのです。 北嶺こそが、これからの日本のエリート教育を牽引する存在であると信じています。

ブラウン大学の留学生の仲間と楽しく過ごす植村さん
僕は高校2年のころから、将来は国際機関で働きたいと考えていました。国際機関で働くには、修士号が最低限必須であると聞き、日米の大学院を調べるうちに、自分の目的にかなうのは、アメリカの大学院に進学することだと気づきました。一方で、僕は帰国子女でもないので、日本の大学卒業後に、アメリカの大学院に行って果たして成功するのか、という不安がありました。そこで考えたのが、先にアメリカの大学に進学して、アメリカのアカデミックな環境で生き抜いていくためのスキルを身につけてから、大学院に挑戦するという進路でした。
しかし、日米の入試制度は大きく異なるため、アメリカの大学進学を選択すれば、北嶺での6年間の努力が報われないような気がしました。そこで、東大に入ることで、けじめをつけてからアメリカへ行こうと決意しました。そして、2011年に晴れて東大文1に合格しました。
ブラウン大学へ
東大は本当に素晴らしい環境でしたが、2011年夏に米国の大学への編入を決めました。入試に必要なエッセイを書く中で、自分は教育に関心があることに気づきました。そこで、学部課程から教育を学ぶことができ、かつ、教育を様々な角度から学ぶことのできるブラウン大学を第一志望で出願し、2012年9月からの編入が認められました。
ブラウン大学で
ブラウンでは、教育政策と経済を専攻しながら、教育を様々な角度から(社会学、心理学、経済学、比較教育学、政治学など)見ています。最終的に、教室の中でどのような変化が起こるのかを念頭に置きながら、政策としてのアプローチを検討しています。ブラウンでは、教育に関する知識のみならず、政策を考えるものとして、いかにして考えればよいのかを深く学べています。

UC Berkeleyのシンボル Cal Bear像とともに
アメリカのカリフォルニア大学バークレー校にて、政治学と経済学を勉強しています。東京大学を一年間休学し、こちらの現地学生とともに授業を受けています。バークレーのほとんどの授業は、教授によるLectureと、20名ほどのクラスに分かれて行うDiscussionから成っており、与えられた問いに対し解答するだけでなく、自ら問いを立て、知識とロジックを使い自分の頭で瞬時に考えることを強く求められます。たとえば「東アジア諸国にみられた急激な経済発展が、他の地域や時代で見られないのはなぜか」、「アメリカの憲法システムは独裁政治を防ぐことができるのか」といったテーマを、学問的な手法とアイディアを両輪にして考えていきます。日本の大学では訓練しにくい能力であるため非常にチャレンジングですが、世界中の才能豊かな学生たちと切磋琢磨できる、最高の機会です。
こちらで強く感じることは、人との出会いが、自分を取り巻く環境を変化させていくということです。出会いから、1人では思いもよらなかった新しい考え方を知り、将来の新たな選択肢を増やすことができます。良い大学に進学したこと、留学を決め海外で勉強していることの本質的な価値は、より多様な人間、優秀な仲間に巡りあうことであるように思います。高い嶺に挑戦した先には、同じく挑戦を経た素敵な仲間が待っています。そして彼らからエネルギーをもらって、自分のやりたいこと、もっと面白いことにさらに挑戦できるのです。
中学・高校時代は、近視眼的で、様々な可能性や選択肢に目を向けることがあまりできませんでした。しかし、北嶺での部活動や受験勉強を通じて、勇気を出してチャレンジする力と、そのチャレンジを継続する力の2つを身につけることができたように思います。この2つの力は、どんな環境においても僕を支えてくれる、強力な土台になっています。北嶺という環境で、素敵な仲間とともに、ぜひ「挑戦」してみてください。

香港からの留学生仲間と佐竹さん

所属する大学のホッケークラブの仲間達と柳井さん(中央)
東京大学から交換留学生としてオークランド大学で、主に太平洋諸国家(フィジー・サモア等)の社会・文化について勉強しています。多くの人々に「どうしてアメリカじゃないの?」「どうしてイギリスじゃないの?」と尋ねられますが、むしろ「どうしてニュージーランドじゃだめなの?」と私は思います。私は英語力向上のために留学を決断しました。ではそもそもなぜ英語を学んでいるか?それは、より多くの人々と友達になりたいから!オークランドは先住民マオリ族をはじめ、太平洋諸国家、アジア、欧州等多様な民族からなり、国籍を越えて様々な人々と友達になるにはまたとない都市です(大学在学中にサモア人の友達を持つとは夢にも思っていませんでした)。
しかし、言語の習得はハードかつ時間を要します。北嶺では、同じ環境で六年間、英語のみならず他教科を含めて、個人添削を含めてより集中的に勉強する環境を得ることができました。
北嶺は「進学校」、すなわち良い大学に入るための学校として認知されています。しかし、良い大学に入る事がそんなに重要なのか?私自身、在学中幾度も考えては両親と衝突しました。大学に入学した私にとって大学は、様々な機会を掴むためのチケットを提供してくれる場所です。そしていわゆる良い大学とは、より多くの、優れた機会を提供してくれる大学で、だからこそ良い大学に進学する事を目指すべきなのだと思います。
また、北嶺在学中に聞いた、「ただ良い大学を目指すのではなく、一社会人として立派な人間になって欲しい」というある先生の言葉がいまだに私の心に残っています。

サモアで子供達と交流する柳井さん

天安門前にて
大阪大学から国費留学生として中国の北京大学で国際関係学を専攻しています。近来、北京は急速な発展を遂げ、地下鉄の総延長距離では世界一になり、街には500万台もの自動車が蠢き、2000万人もの人々が生活する一方で、天安門や故宮をはじめとした歴史的遺産や路地に入れば昔ながらの石造りの町並みが広がっています。そんな新旧が入り乱れた大都市で、現地の北京大生と世界数十カ国から来ている留学生とともに授業を受けています。授業は全て中国語で行われ、テストやレポート・その他発言など高度なレベルを要求されています。
みなさん中国というとどのようなイメージを想像しますか?
多くの人はネガティブなイメージを持っているでしょう。お国柄上、どうしてもポジティブなイメージを持ちにくいですし、隣国ゆえに領土問題を抱え、政府間関係はここ数年特に良くない方向に進んでいます。 しかしこういう予測指標があるのを知っていますか? 「現在のアメリカの経済規模を1とした時に、2050年の中国の経済規模は10になっていると・・。」あくまで予測指標の一つでしかありませんが、飛行機に乗るとたった3~4時間で行ける隣国にそう遠くない将来、ものすごい経済規模の超大国が生まれるのです。当然、内政にたくさんの問題を抱えていますが、間違いなく21世紀は中国を含めたアジアの時代が訪れます。 「アジアに生きるひとりの人間として日本はいかにベストな指針を取るべきか。」ざっくりといえば、現在そのようなことを学んでいます。 なかなか難しい分野ですが、日本とは価値観の異なる海外で勉強するということは、将来を有意義にする一つの手段になりますし、なんといっても考え方の全く異なる優秀な外国人と友達になり寝食を共にし、意見を戦わせるということはゾクゾクするものです。
「世界でチャレンジすること」と「継続は力なり」この2つが現在の自分の行動指針になっていますが、それらを教えてくれたのは言うまでもなく北嶺です。 授業内外で、海外を渡り歩いた多くの教科担当の先生が世界の広さを教えてくれました。そして、2週間に渡る海外修学旅行。生の英語を学んだり、国連を見学したり、観光したりと、非常に濃密で間違いなく忘れることのできない思い出になるでしょう。これらを通して「世界でチャレンジすること」に興味を抱いたのは間違いありません。
北嶺は勉強だけではありません。登山活動や校技である柔道やラグビーを通して勉強では教えてくれない「何か」を学ぶことができます。特に自分は6年間柔道部に所属し、その「何か」を追い続けました。卒業時に感じたこととしては、1つのことをやり遂げた爽快感がこみ上げると同時にその「何か」が言葉では表せないもののなんとなく理解できたような気がしました。現在も飽き足らず、大阪大学柔道部に所属して柔道を継続的に取り組み、文武両道に少しでも近づくように精進しており、顧問の先生が仰っていた「継続は力なり」という言葉が今でも身に染みています。

最後になりますが人生の土台となる時期に北嶺という素晴らしい環境で素晴らしい先生方や友人とともに6年間過ごせたことを今でも誇りに思い、そして感謝しています。是非みなさんも北嶺でたくさん学んで世界に飛び立ってください!
私は北嶺在学時にはアメリカの大学で国際関係学を勉強しようと思っていましたが、新型コロナウイルスの流行や経済的な理由から諦めることになり、それでも海外で学びたかったため、全ての授業を英語で行い1年間の交換留学を卒業要件とする国際教養大学に進学しました。そして3年次にノルウェーにあるオスロ大学に留学をし、英語の歴史(主に約1000年前の英語について)を学びました。

オスロ大学構内の広場
「なぜノルウェーで英語なのか」「なぜ古い言語を学ぶのか」「そもそも国際関係学はどこへ行ったのか」など疑問はたくさんかと思います。国際関係学への興味がなくなったわけではありませんが、大学のフランス語の先生の影響で言語学や古典言語への関心が煽られ、最終的に北嶺時代に好きであった英語と世界史が融合した「英語の歴史」という分野に惹かれたのは必然なのかもしれません。ノルウェー語を含むゲルマン語は古英語と言語的な共通点が多く、ノルウェーは英語圏ではないもののこの分野への入り口にふさわしい場所でした。

留学先でできた友人たちとオスロを一望できる展望台へ
1年間でノルウェーや世界の全てをわかることは当然できませんが、私の考え方や生き方に少なからず影響があったことは確かです。ノルウェーが位置する北欧はスローライフや幸福度の高さで知られています。実際、多くの人が自分のやりたいことを好きな時にやりたいようにやっているため、自信があり心に余裕があって幸せそうであると同時に、他者に対しても寛容で周囲の夢を応援する姿勢が印象的でした。日本にいると、高校を卒業したら少しでも偏差値の高い大学に行って4年で卒業して大企業に新卒採用されなければ、という考えに縛られがちですが、留学を経て、もっと自分の心に素直に「どこで何をどう学びたいのか」、「学びに限らず20代という時間をどう使いたいのか」と問うようになりました。
北嶺での日々や友人は今でも私の挑戦の大きな支えになっています。もう二度と繰り返したくないと感じるほど大変だった受験勉強や、柔道・ラグビー・登山行事を通じて鍛えられた強い精神力で、多くの障壁や逆境を乗り越えてくることができました。また、北嶺の優秀な同期たちがそれぞれの場所で頑張っている様子は、私にとって最高の刺激かつモチベーションになっています。

日本食屋でアルバイトをして海外で働く体験もしました
将来についてはまだ白紙ですが、英語における歴史言語学の本場であるイギリスでもう少し学びを深め、英語に限らず複数の言語を使いながら世界を股にかけて生活することが現在の夢です。10年後くらいまでにその夢が現実となり、このホームページを更新できるよう、これからも精進していきます。

北嶺の登山経験を生かしながら絶景を求めてハイキングをしていました